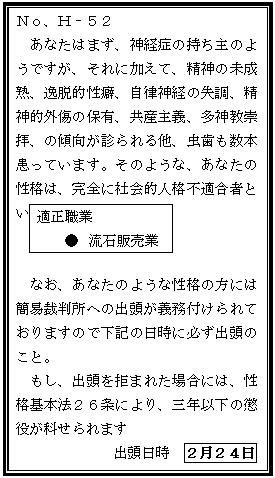
石の駒
あなたは、最近の政治的問題に関心がありますか?→YES
NO↓
隣の夫婦喧嘩は見て見ぬふりをする方ですか?→NO
YES↓
てんぷら油の処理はちゃんと行っている。→NO
YES↓
どちらかといえば趣味は多い方だ。→NO
YES↓
金縛りにあったことがある。→YES
NO↓
形にこだわる方だ。→NO
YES↓
朝はパン食だ。→YES
NO↓
冷え性だ。→YES
NO↓
あなたの性格はH‐52であると診断できます。
コンピューターによる簡単な心理テストが終わると、奥の部屋から鋭い目をした精神科医が、まるで氷の上を滑るように現れて、診断結果を記した紙を僕に渡すのと、そのまま、再び奥の部屋に戻っていったのは、ほとんど同じ瞬間で、その内容は右のようなものでした。
再び奥の部屋に戻っていったのは、ほとんど同じ瞬間で、その内容は右のようなものでした。
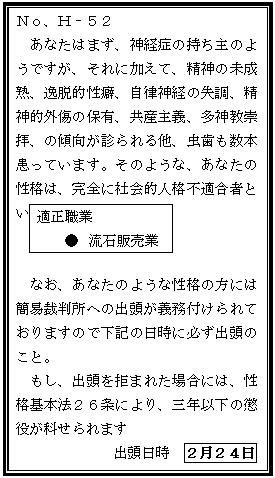
2月24日、性格検査の書類の内容は、かなり憤りを覚えるものでしたが、僕はこんなことで逮捕されても詰まらないので、言われたとおりに隣町の簡易裁判所に出向いていくと、そのまま法廷に連れて行かれ、
「被告に流石販売三年を言い渡す。」
裁判官は、眉の形一つ変えることなく、僕に判決を言い渡しました。
「どういうことなんですか、僕には身に覚えなんて、だいいちあんなものは、単なる心理テストなんでしょ、それなのになんで、ちょっと放してくださいよ、やめてください。だいいち何なんです、流石販売って、そんな職業……いや、裁判所で言い渡すくらいだからこれは、懲罰なんですか、答えてくださいよ。」
僕の手をがっしりつかんで、引っ張っている警察官は、
「いいえ、これは適正職業処置によって行われものですから、社会のためであり、同時にあなたのためでもあるんですよ。」
「冗談じゃない、何で僕が、だってあんなテストでなにが分かるっていうんですか。」
「何でも分かりますよ。」
「はっ?」
「あれは有名な学派の有力な学者さんが考え出した方法でね。」
「だから、なんだっていうのさ。」
「その学者は、なんと十代後半に博士号を取得しているんですよ、すごいもんじゃじゃないですか。それにあの裁判官だって大学は一流の……。」
「それが、なんなんですか!」
「ですから……今回もH‐52番はうるさいですね。何時もこうなんですよ、あなたのように流石販売の判決を受けるとこうやって文句ばっかり、ははは、やっぱり当たっているじゃないですか、H‐52番の人たちって相当な社会不適合者なんでしょ。」
それから四時間、僕は護送車に揺られた結果、何やら風光明媚なところまで運ばれてきましたが、そう思ったつかの間、車はブレーキがいかれているのか、なにやらひどい止まり方をすると、そこは川原の淵でした。
「さあ着きましたよ。ここがあなたの新しい職場であり生活の場です。」
例の警察官は、にっこり笑って僕に言いました。
「生活の場って言われても、僕にはちゃんとした家が街にはありますし、職だってもう持っていますよ。」
「でも、これは裁判所の命令だから仕方ないんですよ。」
「そんなぁ、じゃあ今まで僕の住んでいた家はどうなるんです?」
「さあ、私は知りませんよ、でもあなたがこれから住む家は、ほら、あれです。」
僕が言われたとおりに警察官の人差し指の軌跡をたどって目を這わせると、視線の中には川べりにトタンぶきのやくざな屋根を、虫歯みたいに錆付いた釘でなんとか打ちつけた、今にも崩れそうな、見ているだけで可哀想なほどの小屋が退屈そうに建っていました。
「冗談じゃない、僕は文明人なんですよ、あんな家じゃ暮らせませんよ。」
「ははは、やっぱりあなたは、H‐52番の人なんですね、ははは、ダメですよ、文明文明って言ってる人に限って、未開民族や乞食達に対して強力な差別意識を持ってるものなんですから、やっぱり社会不適合しゃだわ、ははは。」
僕は警察官に逆らうわけにも行かず、しぶしぶ川辺に座り込んで、川の流れを見ていると。
ぎいこ ぎいこ ぎいこ
渡し舟は、そんな音を立ながら、波の立たない水面をを滑って進んでゆくのですが、そこに乗っている客は、人の形はしているものの何だか妙に透き通った体の持ち主ようでしたが、それらが向こう岸から帰ってくるということは、ほとんどなく。
だからこそ僕は、向こう岸には本当に帰りたくなくなるほど綺麗なところなのじゃないかと思ったりもしましたが、河の中心あたりからなぜかいつも霧がかかって、向こう岸がどうなっているかなんて、とても見ることはできそうに在りませんでしたし、よく考えれば、ただ、みんな貧乏で、片道しか切符が買えないだけかもしれませんでした。
現実からの逃避のためにそんな具合に、僕が思考を停止させていると、突然、顔も見たことのない一人の女が僕に近寄ってきたのです。
その女の身なりは汚く、またみすぼらしく、とても長くは見ていられるものではありませんでしたが、彼女はどうやら僕に話しかけようとしているらしく、じっと僕の様子をうかがっていました。
「なんだい、用でもあるのか?」
「へっ。」
痺れをきらして僕が声をかけると、突然話しかけられた事に、戸惑っているのでしょうか、女は驚いたように辺りを見回しましたが、僕と彼女の他には、近くに誰も居ないことを確認すると、何やら安堵でもしたしたように僕のそばにすりよって、
「あの、あなたは流石販売の人ですか?」
女は何故か、僕の言い渡された仕事を言い当てたのでした。
「何で、あんたが。」
「私、H‐53番なんです。」
「53番?」
「あなたはH‐52番なのでしょう?」
汚い女の体が擦り寄ってきたので、僕も最初は我慢できずに振り払おうとしましたが、以外にも彼女の体からは、想像した乞食のような匂いは無く、むしろよく熟れた林檎のような香りがしたので、身なりが汚いのも新しい服を買えないからであって、洗濯も水浴びも定期的にしているのだと想像つきましたし、この至近距離から改めて見てみると、顔も体もそう悪くありませんでしたが、しかし何よりも、番号の似ていることが、僕の中に巣食っていた、あの言いようの無い感傷で彼女と一致し、終いには親しみさえも覚えていました。
「ああ、そうさ。」
「本当ですか!」
「まあね。」
「じゃあ、一緒に石を探しましょう。私の仕事は流石販売補佐なんです。あくまでも補佐ですから直接、石を売れませんので、今まで商売にならなかったのですが、あなたがいらっしゃったのなら……それに私今まで一人きりで、これからあなたもあの小屋で暮らすのでしょう、仲良くしてくださいね。」
僕はそれを聞いて、少しでも好意的に女を見たことを後悔しました。彼女もやはり僕の敵でしかなかったのです。
「冗談じゃない、僕はこれから帰るんだ。ここで商売する気もないし、あんたと馴れ合うつもりは無いよ。僕には他に仕事だってもっているんだ、ちゃんとした家もある。」
「そんな、じゃあ私はどうすればいいんですか?」
「しらないね。」
それを聞くと女は急にふてくされ、とうとう僕に、あの敵意を隠すことも忘れてしまい。
「やっぱり、H‐53の人達はそうなんですね。」
「なんだよ人達って。」
「前にも何度か運ばれてきたんですよ、でもみんなあなたと同じこと言って、あなたはここが、どこだか知ってますか?」
「さあ、どこなのさ。」
「賽の河原ですよ、だから鬼が出るんです。」
どうやらこの女は、頭までどうにかしてしまってるようです。
「鬼?」
「そうですよ、みんな逃げ出そうとして鬼に殺されて……河の向こうに……だからあなたは私と一緒に形のいい石を探して、選別して、色をつけてもいいですし、割って削って、形を整えても楽しいかもしれませんね、だから一緒に石を売りましょうよ。お願いです、私このままじゃ仕事にならなくて餓死してしまいます。あなたが望むなら何でもしますから。」
「嫌だねそんな迷信、誰が信じるっていうんだい。」
「にわかには信じてもらえないかもしれないかもしれませんが、これは本当なんです。私達の場合、逃げようとしたときだけ鬼は、ほら、あそこの祠から飛び出してきて、脱走者を殺してしまうんです。」
「ばかばかしい。」
僕は女の粘着質の手を振り払って、川原を歩き出しました。すると前方には、なにやら必死に石積みをしている子供達の大群が、しゃがんで昆虫みたいに、たむろしているものの、皆、遊んでいるわけでもなくわき目も振らずに、石を積むことだけに勤めています。
そして、そんな光景に少しばかり感心した僕は、暫く近くで見ていると、年端の子供が遂に最後の一つをつみ終わろうとしたときです。
女がさっき指差した祠から、青い鬼が飛び出してきたかと思うと、子供が積みおわろうとしていた石の山を、その手に携えた、子供相手には物々しすぎる棍棒で土台から完全に崩したと思うと、すぐに踵を返して祠へと戻ってゆきました。
「はら、鬼は居たでしょう。あの棍棒で何人殺されたと思います?」
女は何時の間にか僕の近くにまで追いついていました。
「本当にトラ柄のパンツを履いてるんだな。」
僕が女に振り返ろうとしたときです。僕の視線が動いたおかげで、今しがた崩された山を作っていた子供の隣で作業している子供の積んでいる、石の山の中に一つ赤くて綺麗な石が混じっている事に気付きました。
そして僕がその子供が建設中の石の山に近づいたときには、山はもうすぐ完成しそうなほどに高く積みあがっていましたが、僕は躊躇いもせずに、その赤い石を引き抜くと、案の定、同時に山は崩れていきました。
「おじさん、なにしてるの!私の山壊すなんて、非道い。」
「何してるのって、どうせ鬼に崩されるんだろ。」
「でも、その石、私のお気に入りなの、返してよ。」
「嫌だね、こっちは遊びでやってるんじゃないのさ。」
僕がそう言いながら周りを見渡すと、他の子供の石の山にも、幾つか綺麗な石がまじって見えました。
「子供ってのは本当にこういうものを集めるのが上手いんだな。」
「ちょっと聞いてるの、おじさん。」
「ちゃんと、石積まないと、鬼が来るぞ。」
それだけ言えば子供なんて可愛いもので、しぶしぶ作業に戻ります。どうやら子供の邪魔をしても鬼が襲ってこないところを見ると、石集めという商売上の名目さえあるのなら、多少のことならば許されるようです。
「あなた、その石、売るの?」
女は少し嬉しそうに聞いて、
「ああ、あんたもこうやって集めれば、楽なもんさ。」
「じゃあ、一緒にやってくれるの?」
「そうだな、鬼に殺されるのもなんだしな、それにここじゃ僕等もどうやら鬼の立場になれそうだし。ほら、この石みてみろよ、餓鬼は沢山いい石持ってるぞ、お前もてつだってくれよな。」
「はい。」
女は喜んで、子供達の石の山から程度のいい石を選んでは引き抜いてゆきます。子供達もさすがに最初のうちは、文句の一つや二つ言ったりしてはきたものの、僕等は間接的にも、鬼の仕事を手伝っているのですから、子供達にもどちらが鬼の前では有利な立場か解っているのでしょう、そのうち文句どころか、怒った顔一つ見せる子供は居なくなっていました。
女は僕以上に激しく子供達の石を奪っていきます。僕も彼女に負けてはいられません、それに何よりここに住むと決めたということは、彼女が流石販売の補佐でしかない以上、彼女の支配権も僕は握っているということです。これは嬉しくて笑いが止まらないじゃないですか。
石を売っている以上、僕は、この川原の地獄の赤鬼であり続けられるのです。